- フレットとは
- フレットの各部名称や役割
- フレットの音を決める仕組み
- フレットの制作会社
フレットとは

ギターの指板(フィンガーボード)についている金属の棒のことを『フレット』と言います。フレットはアコースティックギター、エレクトリックギター、ベース全てに共通した大事なパーツです。
新しく購入したギターも古いギターも同じところを押さえれば同じ音が鳴るのは、このフレットが正確に打ち込まれているおかげなのです。
ギターにもよりますが1つのギターに22~24個ほどフレットが付けられています。フレットを数えるときはヘッド側から1フレ2フレ・・・24フレと数えていきます。
『0フレ』と呼ばれるのはフレットではなく、ナットの部分を差しています。
下画像で言うところの白い部分(画像左端)がナットになります。

ナットが0フレと呼ばれる理由はどこも押さえないで弦を鳴らした場合に、弦の触れている部分が指板上ではナットのみになるからです。つまり”どこも押さえないで弦を鳴らす”(=開放弦と呼ぶ)音を作っているのがナットになるので0フレと呼ばれるのです。
関連記事:【初心者必見】ギターのパーツ名称と役割を覚えよう!ホーンとは?
フレットの役割
ナットが0フレということを説明しましたが、少しややこしかったかもしれません。
そこでまずはフレットがどのような役割で存在しているのかを見ていきましょう。
弦を鳴らした時の音というのは弦がどの距離感で張られているかで変わってきます。
弦を押さえることで弦がフレットに触れます。すると振動は弦が触れたところで止まるのです。押さえた位置までの長さ分しか振動を許さないよ!とするのが弦を押さえるということなのです。
その長さとはブリッジを起点とし、押さえたフレットまでの距離になります。その長さによって音程も変わってくるのです。
例えば机の上から定規を半分ほど出して弾くとバイーンとなりますよね!そのバイーンという音は机から定規を出す長さによって音程が変わっていきます。
フレットも同じ原理で音程を決めているのです。予めフレットを決められた位置に打つことにより弦を押さえたときにボディ側のフレットに弦が触れることによりブリッジからそのフレットまでの距離の音がなるのです。

フレットがあることにより、初心者でもこのくらいの距離感で押さえればこんな音だなというのを知らなくても、安定して決まった音を出すことができるのです。
フレットは消耗品?
指板に直接埋め込まれ、取り外すことすら難しそうなフレットですが、実はフレットは消耗品になります。
フレットは金属なので長年使っていると弦とこすれることで次第に削れていきます。(特にチョーキングという弦を擦り上げる奏法を行う際に)
フレットが削れていくと音が狂ったり、ビビり(音に雑音が出る)がでたりしますので、交換しないといけません。
多少の削れや、弦の跡、汚れとかならフレット全体をやすりで少しづつ削って均一にしてあげれば良くなります。お店とかでは均一にすることを『すり合わせ』と言います。
消耗品と言いましたが、実際に交換に至るまでには10年単位くらいの話なので特に気にしなくても良いんですけどね!
(じゃあ消耗品とか言うなよと聞こえてきそうですが、一応周知したかったのです笑)
プロレベルになると余分な力が全く加わらないため、フレットがなかなか削れないそうですが、人によってはガンガン削れたりもしますので、ちゃんとメンテナンスはしてあげましょう!
自力で交換することも可能ですが、リペアショップや、楽器店などに持っていけば料金はそれなりに掛かりますがやってくれます・・2万円~くらい。。
他にも、先ほど言ったすり合わせや弦高調整、弦交換まで、やってくれますよ!
フレットの材質は、シルバーニッケル(亜鉛などの合金)やステンレス、真鍮(しんちゅう)などがよく使われています。
シルバーニッケルに比べるとステンレスの方がより硬く強度があります。
硬いフレットほど削れにくいので長持ちしますが、音も多少硬質になるので、硬いからいいというわけでもありません!
フレットを作っている会社
フレットを作っている会社は少なく、日本だと『三晃製作所』がほぼほぼ日本のギターのフレットを作っています。海外だと、『ジム・ダンロップ』や『ディマジオ』あたりが有名です!
三晃製作所ではフレット単品での購入も可能で24フレットセットで4000円~くらいで売っています!
ちなみに三晃製作所は、フレットだけでなく眼鏡フレームや模型レール、スキーやスノボのエッジなんかも手掛けています!
↓↓↓↓↓三晃製作所HP↓↓↓↓↓
フレットの各部名称
フレットにも各部に名称がつけられています。

フレットは実はこのようなキノコのような形をしています!
『クラウン』や『ビード』と呼ばれる頭の部分が弦に当たる部分になります。
『タング』は足の部分でココがすっぽりフレットにはまります。それだけでは抜けやすいので、抜け防止のために『スタッド』がついています。『スタッド』の言葉自体は『鋲』という意味で、タイヤやスパイクの裏などにもある突起物のことですね。
そしてフレットを差し込むために指板側に空いている穴のことを『スロット』と呼びます。
『スロット』は『細長い穴』という意味なので、ガットギターのヘッドに空いた穴もスロットと言い、そのヘッドの形を『スロテッドヘッド』と言ったりします。
関連記事:【知識】ギターヘッドの種類とそれぞれの役割を理解しよう!スロテッドヘッドとは?
初期に開発されたフレットはきのこのような形ではなく、正方形のフレットが使われていたそうです。
つまり、スロットの溝とフレットの幅が同じ大きさだったようです。文字からでも想像できるくらいにすぐ抜けちゃいそうですよね!
また大きさによっても名称がつけられていたりします。
『ジャンボフレット』や『ナロートール』など・・・
ジャンボフレットは言葉の通り大きめのフレットで、ナロートールは細長く、背が高いフレットです!
それぞれに特徴があり、弾き心地なども変わってきますので、自分のギターにフレットを一度確認してみると面白いかもしれません!
フレットレスとは
中にはフレットレス(フレットがない)ベースなんかがあったりします。

そもそもベースの原点、コントラバスはフレットレスなんです。
フレットレスはフレットがない分音程の幅がとても広いのが特徴です。指板どこでも抑えたところの音がでますから、当然ですよね。
しかし演奏には知識と経験が必要になってきますので、フレットレス購入したいって方は、難しいのを覚悟で購入しましょう!
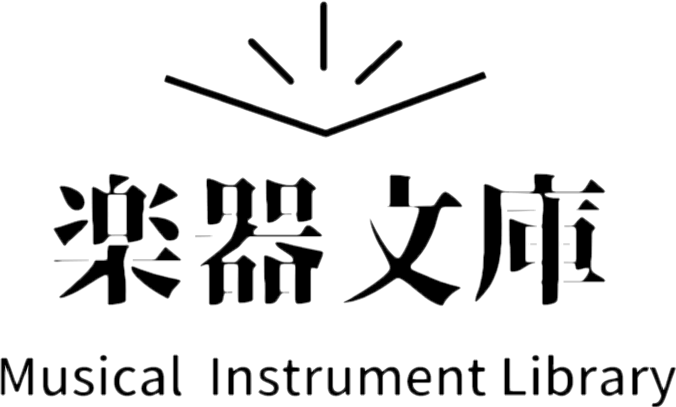



コメント
[…] 【ギター】フレットとは?種類と役割を解説!各部名称も合わせて覚えよう! […]
[…] 【ギター】フレットとは?種類と役割を解説!各部名称も合わせて覚えよう! […]
[…] 【ギター】フレットとは?種類と役割を解説!各部名称も合わせて覚えよう! […]
[…] 【ギター】フレットとは?種類と役割を解説!各部名称も合わせて覚えよう! […]
[…] 【ギター】フレットとは?種類と役割を解説!各部名称も合わせて覚えよう! […]
[…] 【ギター】フレットとは?種類と役割を解説!各部名称も合わせて覚えよう! […]
Thank you for the very useful information